【FP解説】iDeCo改正で掛金上限大幅アップ!2027年施行スケジュールと賢い節税戦略(マッチング拠出/NISA比較)
iDeCo(個人型確定拠出年金)の改正法案(iDeCo 2.0)が成立し、制度が大きく変わります。特に会社員の方の掛金上限が大幅に引き上げられるため、老後資金準備のチャンスです。FPとして、最新の改正スケジュールと、読者の皆様が最も有利に資産形成を進めるための戦略を解説します。
1. iDeCo改正(iDeCo 2.0)の最新スケジュールと主要ポイント
昨年(情報源掲載時)末に可決・成立したいで子改正法案に基づき、厚生労働省から具体的な施行スケジュールの一部が公開されています。特に注目すべき3つのポイントとスケジュールは以下の通りです。
ポイント1:掛金上限の大幅引き上げ(2027年1月実施見込み)
iDeCo最大の目玉は、拠出限度額(掛金の上限)の引き上げです。特に企業型年金に加入している会社員等の「月2万円まで」という縛りがなくなり、ケースによっては3倍増にもなる大幅改正となります。
| 区分 | 現行の目安(月額) | 改正後の上限(月額) (2027年1月実施見込み) |
|---|---|---|
| 企業年金のない会社員 | 2.3万円 | 6.2万円 |
| 企業年金のある会社員・公務員 | 2.0万円 | 最大6.2万円 (企業年金等の掛金との合計で考慮) |
| 自営業者等(第1号被保険者) | 6.8万円 | 7.5万円 (国民年金基金掛金等との合計で考慮) |
| 専業主婦等(第3号被保険者) | 2.3万円 | 2.3万円(変更なし) |
この改正により、会社員や公務員のように2回部分の厚生年金に加入している人は老後の保証がある程度あるため上限が抑えられていたものが、大幅に引き上げられることは「割と嬉しいニュース」となり得ます。
ポイント2:企業型DCのマッチング拠出規制緩和を先行実施(2026年4月予定)
iDeCoの限度額引き上げ(2027年1月予定)に先立ち、企業型確定拠出年金(企業型DC)におけるマッチング拠出の上限規制緩和が2026年4月から先行実施される見込みです。
この規制緩和により、「会社掛金額より個人の拠出額は小さくせよ」という規制が取り払われ、会社員は企業掛金と合わせて月6.2万円の枠をフル活用できるようになります。枠が倍増する人が多いと見込まれます。
ポイント3:加入可能年齢の70歳未満への延長(2027年1月予定)
これまでは65歳未満までだった加入期間が、一定の要件のもとで70歳未満まで延長されます。原則として誰でも70歳まで積み立てられるようになりますが、老齢基礎年金やiDeCoの老齢給付をまだ受け取っていなければ、最大70歳まで積み立てを続けることができます。これは、定年後も働き続けたい方にとって、ありがたい変更です。
2. FPが推奨!最もお得な資産形成戦略(マッチング拠出 vs iDeCo)
FPとしての推奨スタンス:
マッチング拠出がある企業に勤めている方はマッチング拠出を、その他の方はiDeCoを最優先しましょう。
なぜマッチング拠出を優先すべきか
企業型DCのマッチング拠出は、iDeCoと同等の税制優遇(拠出金全額所得控除)がある仕組みです[5, 6]。さらに、多くの場合、iDeCoとは異なり口座管理手数料が原則無料となっており(各社の定めによるが多くは無料)、iDeCoより有利な面もあります。
このマッチング拠出の規制緩和がiDeCoの限度額引き上げに先行して2026年4月に実施されるため、**企業型DCがあり、マッチング拠出制度を実施している会社員の方**は、手数料無料というメリットを享受できるマッチング拠出を最大限利用することが最善の戦略です。
iDeCoを優先すべき人
企業型DCがない方や、マッチング拠出制度を実施していない企業に勤めている方はiDeCoを優先すべきです。
iDeCo最大の魅力は、掛金全額が所得控除の対象となり、毎年の所得税・住民税を安くできる点です。運用益が非課税になる点に加え、この所得控除があるため、iDeCoは新NISAよりも税制優遇が手厚いと言えます。
所得税率は所得に応じて分かれており、所得税率が高くなるほどiDeCoの節税効果が増します。例えば、所得税率20%(年収650万円超の目安)の場合、掛金24万円で年間7万2000円も節税できます。投資は必ず利益が出るとは限りませんが、iDeCoの所得控除のメリットは、所得税・住民税を納めている限り、誰でも必ず受けられます。
3. 60歳までに知っておきたい出口戦略の「10年ルール」
iDeCoは「入口(拠出時)」「運用中」「出口(受取時)」の全てで税制優遇がありますが、受け取り時のルール改正により、出口戦略が「卒業試験」と呼ばれるほど複雑化しました。
5年ルールから10年ルールへの変更(納税者不利の改正)
今回の改正は、iDeCoの税制上の「裏技潰し」であり、一部の人にとっては不利になる内容です。これまで、iDeCoの一時金を受け取ってから5年間空けて会社の退職金を受け取る場合、退職所得控除がどちらにも適用されるという「5年ルール」が存在していました。
この期間が改正により**10年**に伸びてしまいました。
例えば、60歳でiDeCoの一時金を受け取り、65歳で会社の退職金を受け取った場合、改正後は10年経っていないため退職所得控除がフルで使えなくなり、支払う税金が増えてしまうことになります。
これにより、iDeCoの出口戦略(最も手取りが増える戦略)は人によって異なり、専門家への相談が推奨されています。
4. iDeCoと新NISAはどちらを優先すべきか?(年齢・年収基準)
iDeCoは所得控除メリットが大きいものの、原則60歳まで引き出せないという大きなデメリットがあります。新NISAはいつでも引き出しが可能で、投資の自由度が高いです。優先順位は、年齢や年収によって判断することが推奨されます。
年齢別の優先順位
- 20代・30代は新NISAを優先: 住宅購入などライフイベントが多く、いつでも引き出し可能なNISAが適しています。また、iDeCoは口座管理手数料がかかるため、投資額が少ないうちは手数料負担が重くなります。
- 40代・50代はiDeCoを優先: 老後資金の確保に主眼が移り、高年収で所得税率が高い時期であるため、iDeCoの所得控除メリットを最大限に享受できます。
年収・属性別の注意点
- 年収が高い人は、所得税率が高いためiDeCoの節税効果が大きく、iDeCoを優先するメリットが大きくなります。
- 専業主婦等(第3号被保険者)や所得税・住民税が非課税となる方は、iDeCoの所得控除の恩恵を受けることができないため、NISAを優先して使う方がいいでしょう。
家計に余裕がある場合は、新NISAとiDeCoを併用するのがベストです。
5. iDeCo口座開設におすすめの証券会社
iDeCoでは、口座開設時(2,829円)の手数料に加え、口座開設後も毎月171円(国民年金基金連合会等へ)の**手数料が必ずかかる**ため、金融機関選びにおいては、**運営管理手数料が無料**で、かつラインナップが充実しているネット証券を選ぶことが重要です。
おすすめのネット証券3選
運営管理手数料が無料であり、iDeCo口座開設先として優位性を持つ主要なネット証券は以下の通りです。
- SBI証券: NISA口座の顧客満足度調査で3年連続1位を受賞しています。iDeCo口座に関しても、口座管理料が無料になり、投資信託のラインナップが充実している証券会社として推奨されています。
- 楽天証券: NISA口座数が業界No.1(2024年12月末時点)であり、2024年の顧客満足度調査で総合1位を受賞しています。iDeCo口座に関しても、口座管理料が無料になり、投資信託のラインナップが充実していると紹介されています。
- マネックス証券: 以前から米国株や中国株の取引に力を入れており、投資信託のラインナップも豊富です。
読者の方には、iDeCoのメリットを最大限に享受するため、**口座管理手数料が無料であること**を最優先に証券会社を選ぶようにアドバイスすることが効果的です。
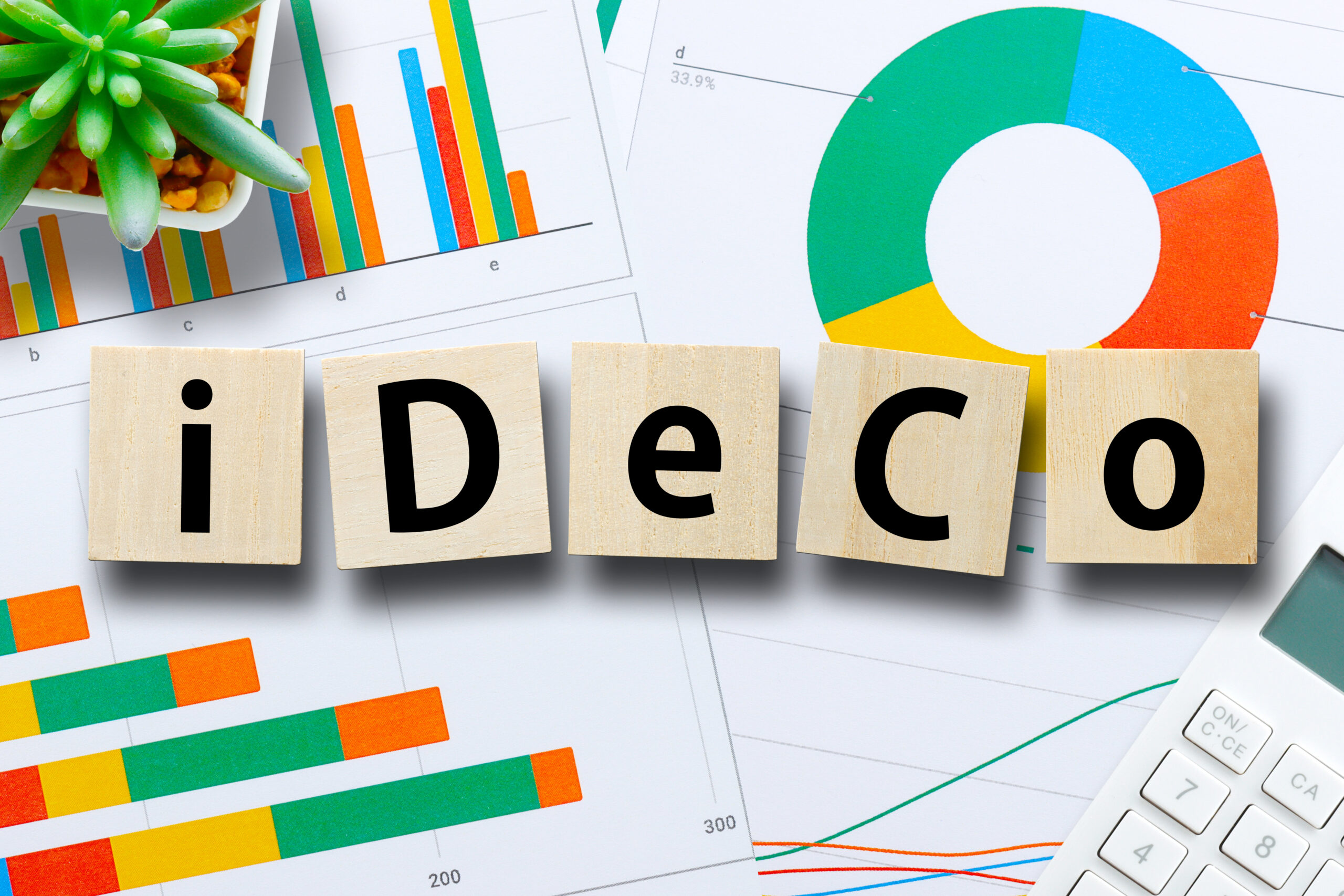

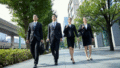
コメント